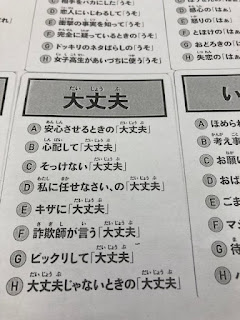【2022.6.11】不条理劇
次回作をどんな作品にするか、作品イメージを共有するための村上さんオリジナル短編の読み合わせが続きます。今日は村上さん書下ろしの「不条理劇」を読み合わせしました。 「不条理劇」を一言で説明するのは難しいのですが、1950年代に書かれた、古典的な演劇概念を破壊し、一世を風靡したサミュエル・ベッケットの『ゴドーを待ちながら』などが代表的です。この時代のこうした傾向の作品群は不条理劇の一派ではあるのですが「アンチテアトル(反演劇)」と呼ばれることもあります。フランスのパリから広まりました。辞書によると、「登場人物が自己同一性を、言語がその伝達能力を、時間・空間が現実性を失って、演劇そのものも不条理となる」作品で「しかし、既成の演劇の主題であった日常的な心理や性格の描写とそれに伴う物語を排することによって、人間の置かれた根本的な状況についての問いかけを純粋に舞台化した点で、むしろ演劇の原点に帰る試みであるともいえる。」とのことです。 わかりましたか? わが国では、別役実さんがその代表としてよく語られます。 さて、読み合わせの結果は、みなさんあまりピンとこない様子で、あっさりと候補からは脱落してしまいました。(残念です) ところで、前々から思っていたのですが、ハロルド・ピンターなど、アンチテアトルの影響を受けた作品が、根強く今も上演され続けるのがちょっと不思議です。プロの上演は見ていないのですが(きっと興行的に成功しないのでしょう)。アマチュアの作品を何本か見ましたが、成功してるのは皆無と私には思えて(残念です)、なぜ上演したかったんだろう?とそんな作品を見るたびに思います。 そういう私も、若かりし頃エドワード・オールビーなどをやってみたことがあります。当時は面白さがわからないのに「すごそうだから」やってしまいました。若気の至りでした。(残念です) でも今頃になってやっとその面白さが分かるようになりました(たぶん)。それを演じる難しさも。 これらの作品を味わったり、上演したりするには演劇経験の積み重ねが必要なのかもしれません。そういえば、パリではイヨネスコを専門に上演している劇場があります。(少なくとも20年前ぐらいまではありました)不条理劇がそんなに長いこと上演し続けられることがまず驚きでした。それで、フランス語のわからない私が、わざわざフランスで不条理劇を見ると...